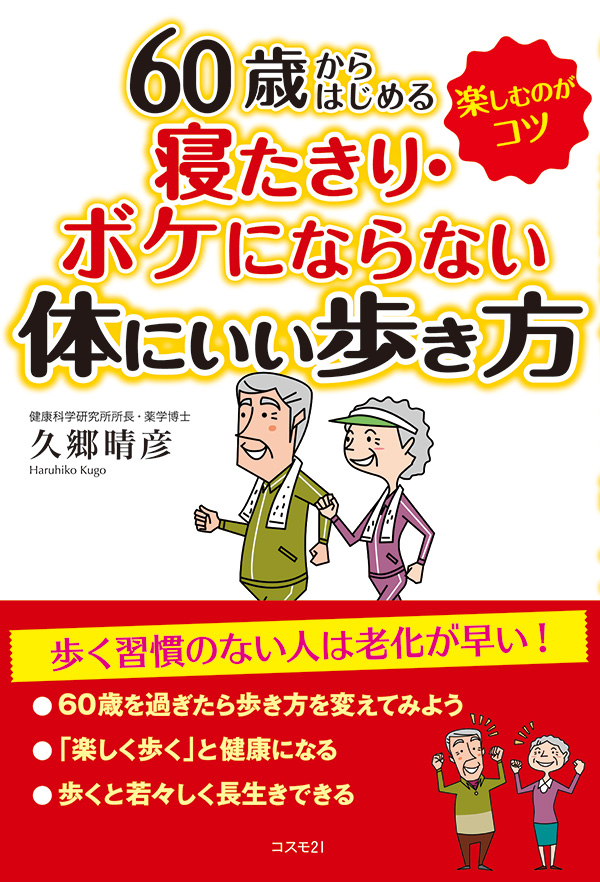60歳からはじめる寝たきり・ボケにならない体にいい歩き方
60サイカラハジメルネタキリ・ボケニナラナイカラダニイイアルキカタ
楽しむのがコツ
久郷晴彦著
歩く習慣のない人は老化が早い!
米寿を迎える著者は、40年以上風邪を引かずに過ごしている。「平均寿命」は世界のトップクラスの長寿国になった日本だが、健康な体で自立した生活ができる「健康寿命」となると覚束ない。健康長寿のために、歩くことの健康効果や60歳からの体にいい歩き方ではなく、健康現役の著者が長年続けてきた毎日「楽しく歩く」コツを紹介する。
立ち読み
はじめに
☆歩くことは人間らしく生きるための基本
私たちは世界でトップクラスの長寿国、日本で暮らしています。ところが、人生の晩年期をどのように過ごし、最期のときをどんな形で迎えられるか、不安を抱いている方は多いと思います。
その日も元気で歩きながら過ごし、夜眠りについたまま、ピンピンコロリとこの世から旅立つことができれば、どんなにいいでしょうか。
ところが、人生は思うに任せないものです。高齢期に寝たきりや認知症になる割合はますます高くなっています。
寝たきりになると、いちばん辛いのは自由に歩けなくなることです。人類は四つ足から二本足で歩くことで人間としての歴史をスタートしました。ですから、歩くことは人間らしく生きるための基本的な欲望なのです。
では、いつまでも元気で歩ける体でいるためにはどうしたらいいのでしょうか。答は簡単です。ふだんから、よく歩くこと、しかも楽しく歩くことです。
☆世界の長寿者に学ぶもうひとつの健康法
米寿(88歳)を迎える私は、40年以上風邪を引かず元気で過ごしています。健康長寿が私の研究テーマで、健康に関した著書も多数執筆し続けています。講演依頼があれば、北海道から沖縄までどこでも伺いますが、ほとんど日帰りです。早朝家を歩いて出かけ、夜遅くになっても歩いて帰ります。その途中の移動もできるかぎり歩きます。
私は生後4カ月で父を亡くし、母の手で育てられました。戦争中は食料不足で私自身病気になり、大切な兄と親友は戦争と結核で亡くしました。そんな少年期の体験を通して「生命とは何だろう?」「ヒトはなぜ病気になるのか?」と考えるようになりました。
その後、薬学の研究が専門になりましたが、生命と健康に関する研究は生涯のテーマです。そのために世界各地の長寿者たちの調査をしたこともあります。そのほとんどの地域は、高山地帯や寒冷地が多く、和食から中華、洋食とさまざまな料理を楽しめる日本と比べたら、食べ物はびっくりするほど質素です。
移動手段は、それほど交通機関が発達していないため、もっぱら歩くことです。かなり遠くにでかけるときも歩きです。高齢になっても、ほんとうによく歩きます。
そんな生活は、文明の最先端にある私たち日本人のものと比べると、とても快適そうには見えないでしょう。それでも、いつも笑顔を絶やさず健康に暮らし、寝たきりや認知症などほとんど関係なく、ゆったりと晩年を迎えます。
その秘密はどこにあるのでしょうか。ひとつは食生活です。なかでも最初に注目されたのが乳酸菌です。今でこそ乳酸菌がいいことは当たり前のように知られていますが、はじまりは20世紀初頭に、ブルガリアの長寿者が毎日ヨーグルトを大量に摂っていることが知られたからです。
和食が注目されるようになったのも、日本の長寿者の食生活が穀類、野菜、魚介類などを主食としてきたからです。
それに比べたら、長寿者たちがよく歩くことは、それほど注目されないままでした。あまりに当たり前すぎたからかもしれません。
☆60歳を過ぎたら歩き方を変えてみよう
2005年のWHO(世界保健機関)の発表によれば、日本人の「平均寿命」は男性が78・63歳で、女性が85・49歳です。日本は世界トップクラスの長寿国になったのです。
ところが、健康な体で自由に歩くことができ、自立した生活ができる「健康寿命」となるとそうはいきません。「健康寿命」は「平均寿命」から「病気期間」を引いたものです。日本の「病気期間」は平均8〜10年で、世界平均の3倍ともいわれます。人生の最後に、それほどの期間を自由に歩くこともできず過ごしているのです。
その病気の代表がガンです。日本人の病気による死亡者の二人に一人はガンで亡くなっています。これだけ医学が進んでもガンの発症率が下がる傾向はいまだ見えてきません。
ガンも含めて死亡原因の上位を占める脳卒中や心筋梗塞などはみな生活習慣病です。その主要な原因が生活習慣そのものにあります。ですから、ここから改めないかぎり、本当には病気を改善できないし、予防することはできません。
生活習慣のどこを変えたらいいのか、たくさんの情報が出回っていますが、88歳になる今日まで健康現役を実践したきた私が、ぜひおすすめしたいのが歩く健康法です。
1日1時間以上歩いている人は要介護の期間が短いという研究報告(2005年発表)があります。
死亡前の要介護期間が6カ月以上の人を調べたところ、1日1時間以上歩いていたグループでは24%の人が該当していました。ところが、30分から1時間未満のグループでは30%の人、30分未満しか歩く習慣のないグループでは41%の人が該当していました。
つまり、1日の歩行時間の長い人のほうが亡くなる前に介護を受ける期間が短いということです
なんだ、そんなことかと思われますか。たしかに歩くことは、きわめて単調な動作ですし、誰でも、いつでもできることです。仕事や家事、趣味など、これまでたくさん歩いてきたから、これ以上歩かなくてもいいだろうと思われる方もいるでしょう。
しかし、60歳を過ぎたあたりからは歩き方を変えてみるのがいいと思います。ただ移動する手段として歩いていたとしたら、これからは、歩いている自分を意識しながら歩いてみてください。足の動き、呼吸、周りにある景色など、歩いているからこそ感じられる世界がたくさんあります。
☆「楽しく歩く」のが続けるコツ
とはいっても、「歩くのがいいのはわかっているんだけど、なかなか続かなくてね」という方がおられます。とくに60歳を過ぎてくると、体を動かすのが億劫だとか、今日は体調が悪い、天候が悪いので家でごろごろしていたいといったふうに、歩かないで済ませる理由が増えてきます。
私は歩く機会を増やすいちばんのコツは、歩く楽しさを見つけることだと思っています。そこで、本書では、歩くことの健康効果や60歳からの体にいい歩き方だけでなく、88歳を迎えた私が長年続けてきた毎日「楽しく歩く」コツを紹介したいと思います。
ここで有名な2つの詩の言葉を紹介します。
「人は自然に遠ざかるほど、病気に近くなる」(ゲーテ)
「青春とは年の数にあらず、心の在り方である」(サムエル・ウルマン)
本書が、健康長寿へ踏み出す楽しい歩き方ガイドになることを願っています。
目 次
もくじ・・・60歳からはじめる寝たきり・ボケにならない体にいい歩き方
はじめに
歩くことは人間らしく生きるための基本
世界の長寿者に学ぶもうひとつの健康法
60歳を過ぎたら歩き方を変えてみよう
「楽しく歩く」のが続けるコツ
パートⅠ 「寝たきり長寿」から「歩ける長寿」へ
歩く習慣のない人は老化が早い
昔の人はほんとうによく歩いた
どうしてこんなに歩かなくなったのか
60歳を過ぎたら“生活のために歩く”から“歩くことを楽しむ”に転換
○歩いている自分の体を意識しながら歩く
○周りを感じながら歩く
○体の声に合わせて歩く
○歩く励みを見つける
○通える場所を多くする
歩くことには老化防止に必要なすべてが備わっている
●コラム 健康の主役は自分自身
パートⅡ 60歳からの体にいい歩き方12箇条
いちばん楽な姿勢で歩く―あまり気にすると歩き方がぎこちなくなる
歩くのに合わせてリズムよく呼吸―ふだんの呼吸をチェックするチャンス
速歩を心がける―歩くスピード、適切な心拍数
歩くコースを選ぶ―体のコンディションに合わせる
季節に合わせて服装を選ぶ―ファッション性と体調管理の両面を考える
足に合ったシューズを選ぶ―実際に履いた感覚を大事に
食事を終えて30分を目安にする―歩いたあとの食事は1時間後
できるだけ同じ時間帯に歩く―習慣化しやすい
適度に水分補給をする―体温調節と脱水症状対策に注意
マンネリ化しない工夫をする―歩くのが楽しくなるグッズや仲間歩き
歩き方に変化をつける―裸足で歩く、水中ウォーキング
自然の中を歩く―森林・山・砂浜……
●コラム 死も自然の営みの中にある
パートⅢ 「楽しく歩く」で11の健康効果
筋力が増し、新陳代謝が活発になる
関節の柔軟性が高まり、平衡感覚がよくなる
体の歪みが取れ、姿勢がよくなる
骨が丈夫になり、骨折防止になる
腸が活性化し、消化、排泄がよくなる
循環機能が活性化し、血圧が安定
心肺機能が向上し、酸素の摂取量も増える
脳が活性化し、ボケ防止になる
ストレス発散になる
肥満予防、糖尿病予防になる
免疫力、自然治癒力が高まる
●コラム 薬は飲まないにこしたことはない
パートⅣ 「歩く」に秘められた若々しく長生きできる4つの秘密
1 よく歩く人は腸が元気
〈元気な腸が健康の基本〉
〈腸には免疫細胞が6割以上集まっている〉
〈腸内細菌が腸内環境を決定する〉
〈60歳からの腸を元気にする食生活〉
〈自律神経を整えると腸内環境が安定する〉
●コラム 笑顔を忘れないで
2 よく歩く人は脳が若々しい
〈物忘れと認知症の違い〉
〈歩くと脳の働きが活性化する〉
〈脳にいい食生活〉
●コラム 人から愛され尊敬されることが長寿の秘訣
3 よく歩く人は血管が丈夫
〈実年齢より血管年齢が高い人が増加〉
〈食べすぎに注意し、よく歩くと血管年齢を若く保てる〉
〈血管の老化を防ぐ食習慣〉
●コラム 医師選びを誤ると早死にする
4 よく歩く人は筋力がある
〈筋肉量の減少は生命維持能力を低下させる〉
〈筋力低下による姿勢の崩れも老化を早める〉
〈しっかり歩けば筋肉づくりは何歳からでも可能〉
●コラム 人生を3回生きる
おわりに